チューナーは便利ですが、目視でチューニングしてしまいます。チューナーの針が合えば完了ですが、狂っていても気が付かないです。一方、音叉は耳で合わせます。音を合わせるだけでなく耳を鍛えることもできるのが音叉です。
音叉でチューニングする

技術士
使うことが少なくなりましたが、チューナーが普及する前は音叉でチューニングしていました。
- 音叉は耳でチューニングします。チューナーが普及していなかった頃は音叉でした。
- 某楽器メーカーのシンボルにも使われていますね。マンドリンで使われるのは442Hzが多いです。楽器店に売っているのは440Hzが多く442Hzは取り寄せもあります。

- 音叉を使ったチューニングの手順です。
- 音叉から発するAの音とマンドリンのA弦の音を合わせる。
- A弦のEの音とE弦のハイポジションのE音を合わせる。ハーモニクスを使ってE音を合わせる。
- A弦ハイポジションのD音とD弦のD音をハーモニクスで合わせる。
- D弦ハイポジションのG音とG弦のG音をハーモニクスで合わせる。
- マンドリンは音が切れやすい楽器のためハーモニクスが使えないと音を合わせることができません。
- 各弦の開放弦で合わせるのもありですが、基本は7フレットをハーモニクスで鳴らします。その方がハモリやすくわかりやすいためです。
チューナーで確認する

技術士
音叉でチューニングした後にチューナーを使い答え合わせをします。これで自分の耳が正確かどうかわかります。
- チューナーを使います。
- 始めからチューナーを使えば良いんじゃない?・・・と言われそうですが、音叉を使って耳を鍛えることが目的のため、チューナーは合っているかどうかの確認のために使います。
- チューニングも練習と思いえば良いです。手順というほどではないですが・・・

- E弦又はG弦から順番にチューニングする。
- ずれていれば音を合わせる。
- チューニング方法は一般的ですが、どの弦が音叉とずれているか認識しましょう。
- ずれている弦の偏りがあります。奏者の癖ですので、修正します。
- 間違っている弦は繰り返しチューニングして正確な音を覚えます。
- マンドリン独奏はE弦がわずかに高くすることがある。響きが良いためである。
- 前提は正確なチューニングができていることである。そのうえでわずかに高くして響きを高める効果を狙っている。
- 一通りの手順を説明しましたので、動画でも説明します。ご視聴いただければ幸いです。
- 5分以内でチューニングできます。チューナーなら1分くらいですが、5分で耳を鍛えられると考えればやってみる価値があります。
音叉のメリットとチューナーだけの問題点
チューナーだけの問題点

技術士
チューナーは耳ではなく視覚でチューニングしてしまうことが問題です。
- チューナーが普及してチューニングが簡単になりました。
- 今は、チューナーアプリもあるからチューナーを買わなくてもチューニングはできます。ただし、チューニングアプリの精度は知らないので事前に調べて使いましょう。
- マンドリンの場合はクリップ式が一般です。クリップをマンドリンに挟むとほぼノイズの影響はありません。使いやすくなりましたね。
- 使いやすくなったチューナーですが問題点にあります。
- 視覚でチューニングしてしまう。チューナーの針を見てチューニングするため。
- 視覚で確認するため、耳で確認しなくなります。チューナーが間違っても気が付かないです。ノイズを拾ってもわからないと思います。
- チューナーを使う場合、最後に各弦のバランスを確認します。開放弦を順番にならして音程が一定であることを確認します。これで、耳を使うことができます。
音叉のメリット

技術士
耳を鍛えることができるのがメリットです。その一方で、時間がかかること、間違っても気が付かないデメリットもあります。
- 音叉のメリットは耳を鍛えられることです。
- 視覚を使うことがないので耳に頼らざるを得ないです。使えば使うほど耳の強化に役立つのが音叉です。
- チューニングを練習として音叉を使った音感トレーニングする奏者もいます。これも音叉のメリットです。
- 一方、デメリットもあります。
- 時間がかかることです。チューナーのように1分もあればチューニングできるというわけにはいきません。数分はかかります。わずかとは言え嫌がる奏者もいます。
- それと、間違っても気が付かないことです。自分の耳が正確と信じることは必要ですが、チューニング中に外部から影響を受けチューニングが間違うことがよくあります。間違いに気が付くのはチューナーの方が気がつきます。
- デメリットはありますがデメリットを上回るメリットはあると思います。積極的に音叉をチューニングに活用しましょう。
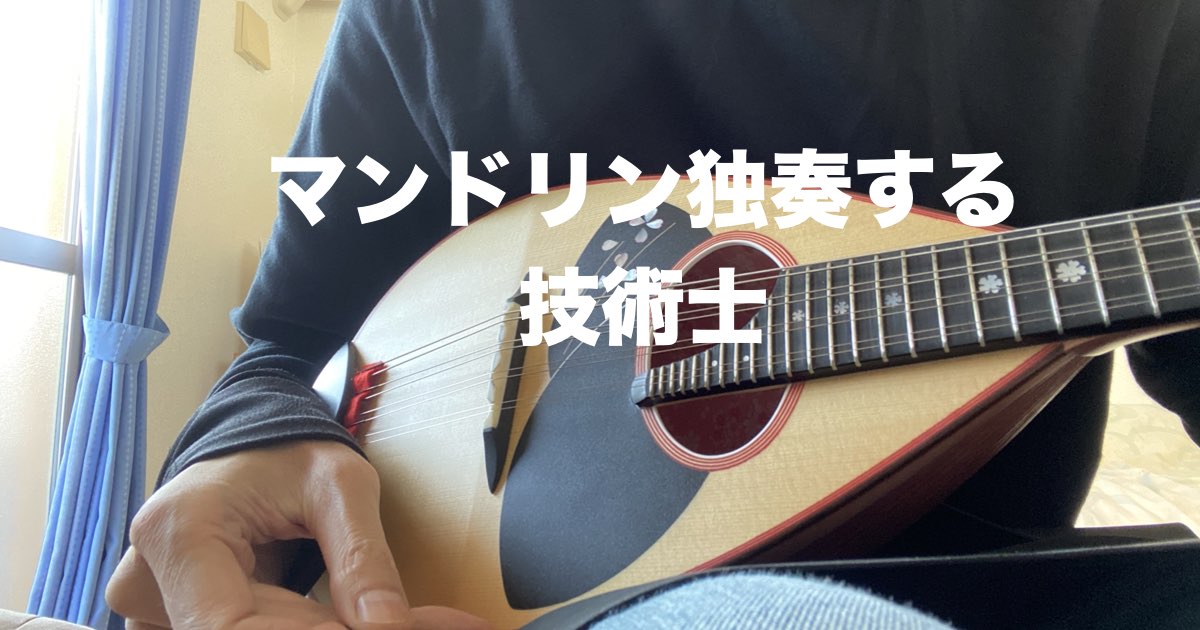

コメント